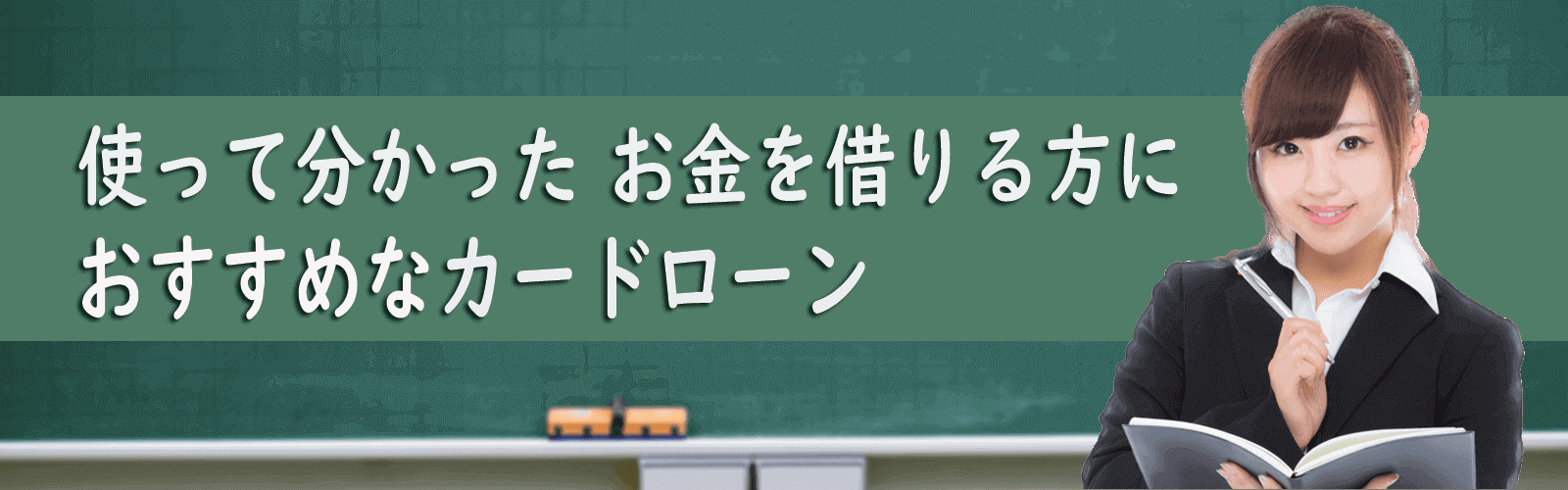失敗しないためのおすすめNISA口座 | ジュニアNISAもあり
2014年にはNISAが、2016年にはジュニアNISAが、2018年にはつみたてNISAがそれぞれ始まりました。
投資には「国策には逆らうな」という格言があります。
老後資金のためにもこれからは投資で資産を増やしたいなら、すぐにでもNISA口座を開きましょう。
ここでは、失敗しないためのおすすめNISA口座と、ジュニアNISA、つみたてNISAについてご紹介します。

■NISAで失敗しないために知っておくこと
NISAはかなりお得な制度ですが、さすがに知識ゼロではやけどの元です。
とはいえ、NISAについての詳しい解説は「なんだか難しいしもういいよ」という方に、どうすれば失敗しないのかをまるっと説明しましょう。
0から詳しく知りたい方は、金融庁のNISA特設サイト(https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/index.html)や証券会社、銀行のサイトをチェックしてみてくださいね。
まずは、NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAのうちNISAについてお知らせします。
・NISAはいつまで?
NISA口座の開設期間は、2023年12月31日までです。2023年の投資分は、2027年まで非課税ということになります。
1年間に投資できる金額は、現在120万円までです。
運用期間は最長で5年間です。
5年の間に売却すれば、それで得た利益はどんなに儲かったとしても非課税です。
・5年後はどうなるの?
では、保有していた金融商品が5年を迎えたらどうなるのでしょうか?
ここ、重要です。
5年後には、選択肢が2つ
1. NISA口座から特定口座、一般口座に移す
2. ロールオーバー(繰り越し)する
があります。
取得から5年は過ぎ、もっと値上がりしそうな場合は、まだまだ手放したくはないですよね?そんな場合はそのまま自前の特定口座や一般口座に移すことが可能です!
もちろん、NISA口座ではなくなるので、課税対象にはなりますが、NISAの恩恵が無くなるわけではありませんので安心してください。
例)
100万円で取得→5年後130万円に(そのまま一般口座へ)→その後150万円で売却といった場合。
通常なら、最終利益である50万円に課税されますが、NISAを通していると…。
NISA口座明けの移管金額が(この場合130万円)取得金額とされ、最終利益の20万円だけに課税されます。
この差は大きいですよね!
もちろん、翌年も新に120万円までNISAを利用可能です。
では、同じ金額でロールオーバーを選んだ場合とは。
例)
100万円で取得→5年後130万円→ロールオーバーで130万円全額延長ということになります。
ロールオーバーすれば、また5年間非課税枠で運用が可能になります。
ただし、ロールオーバーは翌年の枠を使うので、翌年は新たにNISA口座での投資はできません。もちろん、ロールオーバー額が50万円の場合は、120万円-50万円(ロールオーバー分)=70万は新に投資可能です。
ちなみに2017年に法改正でロールオーバー上限が撤廃されるまでは、100万円までしかロールオーバーできませんでした。以前の資料を参考にしている場合は注意してください。
最初は「5年も先のことなんて分からないし、儲けたらすぐに売却するから」と、あまり関係ないように思われるかもしれないですが、投資は山あり谷ありです。
投資の世界で5年なんてあっという間です。常に先のことは意識しておきましょう。
■NISA口座を開く際の注意点
なんでもかんでも税金がかかるこのご時世、ぜひ、非課税のNISAを活用したいところ。
すぐに口座を開こう!というあなた、ちょっと待ってください。
NISA口座は「一人一口座」という決まりがあります。
どこで口座を開いてもNISAの概念は同じですが、取扱商品や手数料が異なるので、テキトウに口座を開設し、後から後悔したなんてこともよくあります。
【NG】
・投資信託と株式に分けたいので二口座欲しい
・1年の内、A証券で60万運用、残りの60万はB証券で運用したい。
そもそも口座は一人一口座。また、A証券でNISA口座を開設した場合、B証券には年が変わらないとNISA口座を開設することはできません。
「一般口座をA証券で持っているからそのままNISA口座も開設したが、投資信託の取扱本数が少なかった。」
「銀行で開いたけれど、ポイントがつく証券会社に申し込めばよかった」
「手数料が異様に高いので、なかなか儲からない」
など後悔しないよう、口座開設は充分に吟味が必要です。
【OK】
・2019年はA証券で運用。2020年はB証券で運用。(A証券のNISA口座はそのまま最長5年運用可能)
すでにイマイチな金融機関でNISA口座を開いてしまっていても、年を超えれば乗り換えも可能です。(2015年より)ただし、乗り換えは1年に1回なので、やはり吟味は必要です。
おすすめ口座はこちら
■NISAには落とし穴はあります!
「国策なのに落とし穴?」と言われそうですが、残念ながら落とし穴は存在します。
「やっぱり。うまい話しだと思った」とも言われそうですが、NISAの落とし穴は気をつければ十分に回避可能です。
なぜなら、すでに落とし穴の場所が分かっているからです。
ここでは、どこに落とし穴が開いているのか解説します。
・配当金に課税?
株式に投資した場合、配当金が貰えることがあり、通常20%課税されます。
NISAを利用した投資の場合も配当金は貰えるのですが、その貰い方によっては20%の税がかかってしまいます。
配当金の受取方は3パターン。
1. 配当金領収書を持って郵便局で現金受取
2. 銀行口座に振り込み
3. NISAをしている証券会社の口座に入金
このうち、配当金が非課税になるのは、3の証券会社の口座に入金のみです。
NISA口座を開く場合、配当金の受取は、「株式数比例配分方式」を選択してください。
指定の銀行口座で受取る「登録配当金受領方式」「個別銘柄指定方式」、ゆうちょ銀行や郵便局で受取る「配当金受領証方式」は選ばないでください。
ただし、ここでも要注意です‼
NISA口座分だけではなく、保有するすべての銘柄の配当の受取り方法が変更となります!
他で一般口座や特定口座を持ち、取引をしている場合は注意しましょう。
悲報
ファンコミ2,500株NISAあるが、配当金非課税にするため証券会社入金設定他の証券会社にある残りの特定口座は現金で配当を貰おうと設定
結果
NISA含め全部課税対象の現金受け取りになる9,500円損したお…
— TERU@ファンコミ&赤坂王子 (@TERU_biz) 2019年3月29日
・損失繰越ができない
株式やFXなどの投資で損失は出た場合は、確定申告によって損失繰越が可能です。
損失の繰越控除とは、本年分の損失を控除しきれないときに、翌年以降にその損失を繰り越して翌年以降の利益から控除することができる制度です。上場株式等の譲渡により発生した損失は、「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」として、損失を出した年の翌年以後、最長3年間繰越して、翌年以後の上場株式等の譲渡益から控除することができます。
引用:SMBC日興証券「初めてでもわかりやすい用語集」
https://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/so/J0079.html
例えば、100万円投資して損切をした場合、50万円のマイナスとなりますが、確定申告で損失の繰越控除をしておけば、翌年から3年間は、利益から50万円分が控除されます。
翌年に30万円の利益がでた場合、その分には課税されません。
簡単に言うと、繰越申請をしておけば、3年間は損失を取り戻すための利益には課税されないということです。
もしも申請をしていなければ、翌年の利益30万円にもしっかりと税金が掛けられてしまいますので、損失を取り戻すには単純に計算しても2割以上の利益を上乗せしなければいけません。
残念ながら、NISAにはこの制度は適用されません。利益に課税されないので、損失にも優遇措置がないということでしょう。厳しいですよね。
・一般口座や特定口座との損益通算ができない
一般口座や特定口座なら、それぞれの口座で出た利益や損失をお互いに相殺できますが、NISA口座との損益通算はできません。
例えば、一般口座で利益が50万あり、NISA口座で損失が40万あるとします。
この場合、50万(一般口座)-40万(NISA口座)=10万円(最終利益)×課税
ということにはなりません。
50万円すべてにきっちり課税されます。「あっちで損しているからまけてあげるよ」という温情はありません!
・損失を抱えたまま5年を迎えた場合
5年もあるから大丈夫かと始めたものの、あっという間に5年が経ち、結局は損しているということあるでしょう。
その場合、ロールオーバーではなく別口座に移管するには注意が必要です。
例えば、50万円で購入後、5年後に40万円に。一般口座に移管後、60万円に値上がり!となった場合、気持ち的には10万円分だけの課税におねがいしたいところですが、実際には、60万円-40万円(移管時の金額)=20万円に課税ということになります。
移管しただけでかなり利益を削ることになり、ショック過ぎます。
・米国株を買う場合
NISAでも証券会社によっては外国株の取扱いが始まりました。
特に米国は経済状態もよく、有名企業も多いので、大人気です。
ですが、NISA口座で米国株を購入すると、まだまだ手数料が高いのが実情です。
売買手数料や、為替手数料(為替スプレッド)などを計算する必要があります。
これらの手数料で利益がほぼ吹っ飛ぶことも。
また、譲渡益は非課税でも配当に10%の税金がかかります!
一般口座や特定口座で米国株を購入した場合は、外国税額控除によって一定額還付されるのですが、NISA口座の場合は容赦なしです!
配当金狙いの場合は、かなりの高配当銘柄を狙わないと、旨味が薄いです。
■NISA天国と地獄
NISAは基本的に課税されない優遇制度なので地獄など無さそうなのですが…。
ネット上の声を調べてみました。
まずはマイナスコメントから。
去年NISAで全力買いして、現在含み損が47万ぐらいのNvidia株の配当が出ましたが円高な事もあり690円/(^o^)\
相変わらず低すぎーー(´・ω・`)
NISAなので損切り出来んのよ(´・ω・`) pic.twitter.com/zLwuPc5Ay9— Master_SP (@master_SP) 2019年6月26日
NISA口座、損切りためらいやすくなるのはデメリット
— エディ@ Stuttgart (@eddie_masa) 2019年6月18日
一時、含み損40万くらいまで膨れ上がって、NISAで買った為に逃げることも出来ずに二年間、ようやく、7000円程度の損切りで逃げれた…。長かった…。(結局損切りだけども…
— 春野うた (@harunouta5) 2019年6月20日
やはりNISAのせいで地獄を見たというコメントは少ないようです。
ですが、NISAなので損切がどうしても遅れてしまうという意見は多いです。
損失の繰越控除が出来ないのは、決断力を鈍らせ、損切できないまま塩漬けする人も少なくありません。
投資にはルールが大切であり、損切は徹底すべきです。ですが、NISAは損失の繰越控除もなく、損切をしたからといって、NISA枠が広がるわけではないので、その機会をどうしても逃しがちになるようです。
次はポジティブコメントです。
JTからの配当金が入金していた。これだけでもうれしいのに、あれれ、なんか金額が多いぞ。と思ったら、税金がゼロ。あっ、そうか、そういえばNISAだったのをすっかり忘れてた。
こういう時ってすっごく得した気分(になりますよね?)。— 正直者 (@bam11300820) 2018年9月5日
【NISA:ニーサとは】
効率の良いお金儲けの手段どこが効率いいポイントかというと、儲けに対して税金かかんない
儲けたら儲けただけ自分のお金になる本来は儲けに対して2割国に納める決まりがあるのだけど、ニーサを使って投資信託を購入すると非課税で丸儲けという夢のような仕組み
— 🦐エビノール🦐 (@hijikimarico) 2019年3月11日
つみたてNISA、じわじわと増えている。金利すごいな。株の勉強もっとしよ。
— K-TOM (@KTOM81947467) 2019年6月24日
ポジティブコメントは、これまでは課税されていた分まで儲けられた喜びや、NISAがいかに嬉しい制度か、またNISAが投資や経済の勉強のきっかけになったことなどが多いです。
また、コメントの中には「つみたてNISA」「ジュニアNISA」に関するものも多く、将来に向けて資産を増やす喜びについて語られています。
■NISAのおすすめ銘柄は?
ますます盛んになるNISAですが、誰もが知りたいのはズバリ「おすすめ銘柄」でしょう。
NISAは利益を出してこその制度なので、ここはしっかり押さえて行きましょう。
・NISAで投資できるもの
NISA口座の利益は非課税であることから、投資にはたいへんありがたい制度です。ですが、なんでもかんでもNISAで投資できるわけではありません。
【NISAが利用できるもの】
国内株式(国内ETF、J-REIT ETN)
投資信託(株式型、債券型、バランス型、コモディティ型など)
外国株式(米国、香港、ロシア、ベトナム、シンガポール、タイなど)
グーグルやアマゾン、ナイキやスターバックスなどにも投資可能です!
【NISAが利用できないもの】
仮想通貨、FX、債券、貴金属など
仮想通貨やFXの利益が非課税なら嬉しいところですが、それはNGのようです。
NISA自体が株価を上げるための国策なので、当然ながら株式以外は冷遇されています。
もっとも、仮想通貨やFXは株式よりもマネーゲームになりやすいので、仕方のないことなのかもしれません。
・初心者なら投資信託
NISA初心者、投資初心者におすすめは、ズバリ投資信託です!
なぜ、投資信託なのかと言うと、プロは運用してくれるので自分ではアレコレ考える必要が少ないからです。
投資を失敗させないコツは分散させることです。とはいえ、素人には銘柄を分散させバランスを取るのは至難の業ですね。投資信託なら、ややこしいことはプロに任せ、後はほったらかしでOK!素人は右往左往して利益を減らすことが多いのですが、投資信託なら、後はどーんと構えて時々運用状況をチェックするだけです。
投資信託の選び方は、大きく分けて2つあり、
・安定運用を目指すならインデックス型
・大きなリターンを狙うならアクティブ型
ということになります。
投資信託には販売手数料や信託報酬、売却時には信託財産留保額などのコストがかかりますが、運用コストが安いものも多いです。
初心者におすすめは断然、コストの安いインデックス型です。
国内株式なら、ニッセイ日経平均インデックスファンドhttps://www.nam.co.jp/fundinfo/nnhif/main.html
先進国株式なら、eMAXIS slim 先進国株式インデックスhttps://emaxis.jp/fund/252653.html
全世界株式なら、楽天・全世界株式インデックス・ファンドhttps://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/rivge/
などが人気です。
インデックス投資を始めて1年ちょっと。
最初は王道の世界分散がいいだろうってことで、TOPIXや新興国株式のインデックスファンドも買ってました。
今はeMAXIS Slim先進国株式インデッスほぼ一本にしてますが、あれこれ考えずにほっておけるのでいい感じです。— Sheena@ほったらかしインデックス投資継続中 (@Sheena_9804) 2019年3月24日
・気になる銘柄があるなら株式投資
応援したい企業や、これはいけると思う銘柄がある人は、株式投資がおすすめです。
株式の場合、株主優待や配当にも旨味がありますが、NISAの場合は、株主優待を狙うよりも出来るだけ高配当の銘柄がおすすめです。
なぜなら、株主優待の基本は長期保有なので、なるべく早く利益を出したいNISA口座にはあまり向いていません。
また、株主優待分はそもそも非課税なのでNISA口座である必要もありません。
NISAで株を買うなら、120万円以下の株で、高配当を基本に選びましょう!
■つみたてNISAとは
2018年1月から始まったつみたてNISA。これまでのNISAとは少々ルールが異なるので、簡単に説明します。
・つみたてNISAの仕組み
つみたてNISAは、長期の積立投資を後押しするために作られた制度です。そのため、従来のNISAの投資期間が5年なのに対し、つみたてNISAは20年と期間が長いのが特徴です。
利用可能枠は、年間で40万円まで。月割りだと最大33,000円になります。
ポイントは大きく分けて3つです。
1. NISAなので、値上がり益、分配金ともに非課税であり、利益を丸ごと得られます。
通常なら約2割が利益から差し引かれるので、20年間運用するとなるとかなりお得になりますね!
2. つみたてNISAの基本は、毎月自動積立で決まった銘柄を購入するパターンです。毎月、自身で設定した日に値動きを気にせず自動で購入されます。銀行口座からの自動引き落としが可能なので、手間がかかりません。
3. 投資する商品は、金融庁が厳選した長期・積立・分散投資に適したものの中から選択します。販売手数料が0円、信託報酬が低い、分配金が頻繁ではないがその条件で、着実に資産を増やすのに適しています。
・つみたてNISAの注意点
「NISAはそこそこ短期投資、つみたてNISAは長期投資で使い分ければいいってことね。早速両方始めよう!」というあなた。少しお待ちください。
実は、NISAとつみたてNISAは併用できません‼
「じゃあ、もうNISAやってるからつみたてできないじゃん。ムダに勉強しちゃったよ」とがっかりしないでください。
同じ年に購入はできませんが、1年ごとに運用を切り替えは可能。要するに年単位でどちらか好きな方を利用できるということです。
とはいえ、つみたてNISAは長く継続してこそだし、NISAはチャンスを掴んでこそです。株価を上げることで、老後資金を個人で捻出するための国策なんだから、そこは太っ腹に併用させてくれてもいいのでは?と正直残念です。
また、NISA同様、損益通算や未使用枠の繰り越しも出来ません。
4.2%って一般に安全と思われているアセットクラスだけだと達成できない絶妙なラインだと思う。
両者を併用できない制度なので、選ぶポイントは自分の投資予算とリスク選好度で決まるんだろうな。年間投資予算が40万以下 or 安全資産での運用なら、つみたてNISA。みたいな。
(おわり)— tomatosoup (@tomatosoup) 2017年12月23日
つみたてNISAよりも従来からあるNISAの方がよいかも。デメリットとして従来のNISAと併用できない。選べる対象が少なく投資信託に限定されている事と運用期間が長すぎるかなと。
— とりあえずFP (@tori22381134) 2019年6月27日
・どんな人におすすめ?
ズバリ「若い世代」です。
つみたてNISAは2037年まで毎年枠が組まれる予定です。
長期投資をしてこそ実り多い設定なので、これから結婚や住宅購入など、ライフイベントが目白押しの若い世代におすすめします。
また、毎月少額投資(100円でもOK!)から始められることも、投資初心者の若い世代におすすめの理由です。
つみたてNISAは種から育てる感覚です。
じっくり腰を据えて育てられる世代こそが大きな実りを得られるでしょう。
■ジュニアNISAとは
2016年から始めったジュニアNISA。子供の将来のために気になるところですが、子供のためだからこそ、失敗するわけには行きません。
ジュニアNISAに落とし穴はないのでしょうか?
・ジュニアNISAの仕組み
未成年でもNISAを活用できるようにと始まったジュニアNISA。利益や配当金が非課税な点や、5年後もロールオーバー可能な点はNISAと同じです。ただし、年間の非課税枠が80万円とNISAの120万円よりも少ないです。
非課税以外のメリットとしては、相続税対策と経済の勉強になるというところでしょうか。
子供や孫にお金を残す際には、相続税や贈与税対策が必要になりますが、その一環としてジュニアNISAは有効です。
年間80万円までの資金提供は税金を気にする必要はありません。投資可能期間はNISA同様2023年までですので、80万円×数年分は非課税で受け渡しできることになります。
ひと昔前までは、相続税や贈与税は一部の富裕層にしか関係のない話でしたが、ここ数年の間に法が改正され、非課税枠がぐっと減り、課税対象となる家族が増えています。
今後、増々厳しくなることは容易に想像できるので、できるだけ早く対策をとっておいてもやり過ぎということはないでしょう。
また、これからの時代、資産運用無くしては、生活が苦しくなることも充分に考えられます。お金に無知でいるよりも、小さい頃から経済に触れさせることは、近い将来、必ず子供達の武器となるでしょう。
基礎控除は2014年まで「5000万円+法定相続人1人あたり1000万円」だったが、15年1月からは「3000万円+法定相続人1人あたり600万円」に縮小した。地価の高い都市部などで課税の対象者が広がっているようだ。
引用:日本経済新聞電子版 2016/1/24「相続税、15年1月から増税」
https://www.nikkei.com/article/DGXLZO96480610U6A120C1NN1000/
子供の頃からお金の運用
小学生の息子に投資教えます!いや、親子共々実践勉強始めます!https://t.co/Wk53USlo16— Nico (@Nico56613504) 2019年6月25日
・ジュニアNISAの注意点
NISAと同じく運用期間が5年、枠の繰り越しや損失の繰り越しは不可ですが、一番の注意点は、「18歳(3月31日時点で18歳であるの前年12月31日)になるまで払い出し制限がある」ことです。
0歳児でも可能なジュニアNISAですが、運用したお金は災害などのやむなき場合でない限り、基本的に払い出しはできません。
もし、それでも払い出しを希望する場合は、
・ジュニアNISA口座の廃止
・これまで非課税で受けた配当金や譲渡益に課税
されることになります。
これまでの配当金に課税されるだけならまだ諦めもつきますが、損失を出している時など、タイミングの悪い解約は損失繰り越しも出来ないため一般的口座や特定口座により投資よりも分が悪くなります。
子供のためにジュニアNISAを始めるのはいいのですが、教育資金などをある程度確保した上での投資をおすすめします。
・どんな人におすすめ?
まずは、生前贈与を考えている人。現金に余裕があり、元本割れのリスクを許容でき、かつリターンを狙う人です。
少しでもリスクがとれない人は、学資保険や定期預金で子供の将来に備えるべきでしょう。
実際、ある程度自由なつみたてNISAにするか、縛りがキツイジュニアNISAにするか悩む人は多いです。
子供の教育費積立という資産形成目的からすると、ジュニアNISAではなく、親のつみたてNISAを使った方が合理的。ジュニアNISAの対象商品はつみたてNISAと同じに規制すべき。ジュニアNISAで個別株は危険すぎる。JDIやぽんつーだって東証一部銘柄だからな。
— オカルティスト (@Occultist905) 2019年6月24日
んー、調べれば調べるほどジュニアNISA微妙…💔わたしのように児童手当を運用したい人にはつみたてNISAのほうが絶対いいよね。5年間で最大400万投資って、株クラさんならいいけどそうじゃない人にはハードル高すぎない?
— よもぎ (@yomogi_toshi) 2019年6月27日
NISAはかなりお得な制度ですが、口座の取得や運用には制限があります。
どのタイプのNISAを選べば一番得するのかは、人それぞれです。
投資目的が、老後資金なのか、ライフイベントなのか、教育資金なのかを考え、自身にあった口座を開くようにしましょう。
■NISAをするならココがおすすめ
投資は、どこで口座を持つかによって、お金の増え方が変わります。
NISA自体は国策ですが、金融機関によって、コストや商品ラインナップ、利用者へのサポートなどは大きく異なります。
ここでは、初心者にもおすすめの金融機関をご紹介します。
・楽天証券https://www.rakuten-sec.co.jp/nisa/
楽天証券では、
・手数料が安い!
・100円から積立投資ができる
・楽天ポイントがたまる
・投資信託の取扱い本数が多い
・ノーロード(手数料不要の投資信託)の取扱い本数が多い
・情報量が多い
・画面操作が分かりやすい
・お得なキャンペーンが多い
・外国株式が買える
が特徴です。
手数料が安いだけでなく、楽天ポイントも貯まるので、楽天ユーザーにはかなりお得です。
オールマイティに投資先が選べ、しかも手数料が安いのでとくにおすすめです。
楽天でつみたてNISAをはじめたよ!かけた金額に応じて1%のポイントが返ってくるし、楽天ユーザーとしてはありがたい🙂
— もな (@monami226) 2019年6月25日
・SBI証券https://site0.sbisec.co.jp/marble/nisa/top.do
SBI証券では、
・手数料が安い!
・100円から積立投資ができる
・SBIポイントがたまる
・投資信託の取扱い本数が多い
・ノーロード(手数料不要の投資信託)の取扱い本数が多い
・情報量が多い
・ジュニアNISAでも外国株式(9カ国)が買える‼
が特徴です。
オールマイティに投資先が選べ、しかも手数料が安いのでとくにおすすめです。貯めたポイントは、商品や現金化、Tポイント等にも交換可能です!
-NISA口座とか持ってて、売買手数料無料の得点があれば、マネックス以外の証券会社でもお得に外国株買えます。とくにSBIはFX口座や住信SBI銀行の外貨得BUY日の安い手数料で調達したドルを外国株口座に振替できますから。
— 菟道りんたろう (@udohrintaro) 2016年6月3日
・マネックス証券 https://info.monex.co.jp/nisa/about/index.html
マネックス証券では、
・米国株式 3,000銘柄超え、中国株式 ほぼ全銘柄が買える‼
・100円から積立投資ができる
・マネックスポイントがたまる
・情報量が多い
・トレーディングツールが高機能
・100株単位や1,000株単位ではなく1株から取引できる
・一流オペレーターのサポートが受けられる
が特徴です。
外国株の取引をメインに考えるなら、マネックス証券がおすすめです。米国株の取扱い数№.1で買付手数料が実質無料です。また1株でも買えるワン株は、憧れの銘柄を手に入れるチャンス!
余裕出てきたら毎月積立で金を買う
あとマネックスにNISA口座を移管して米国株と中国株にも目を向けよう— オモイタチ (@ymnsTL4053) 2018年3月1日
まとめ
お金は、何もしなければ増えません。
しかも減ります。
「使わなければ減らないでしょう」と思われるかもしれませんが、よく考えてください。
子供の頃の500円と、今の500円。金額は同じですが、あの頃と同じようにいろいろな物が買えますか?ほとんどの商品は値上がりし、当時10個買えたものが、今は5個しか買えないなんてザラです。
何もしないで時間が経つと、お金の実質的な価値は下がってしまいます。
不安のない将来のためにも、上手くNISAを活用し、コツコツと資産を積み上げましょう。